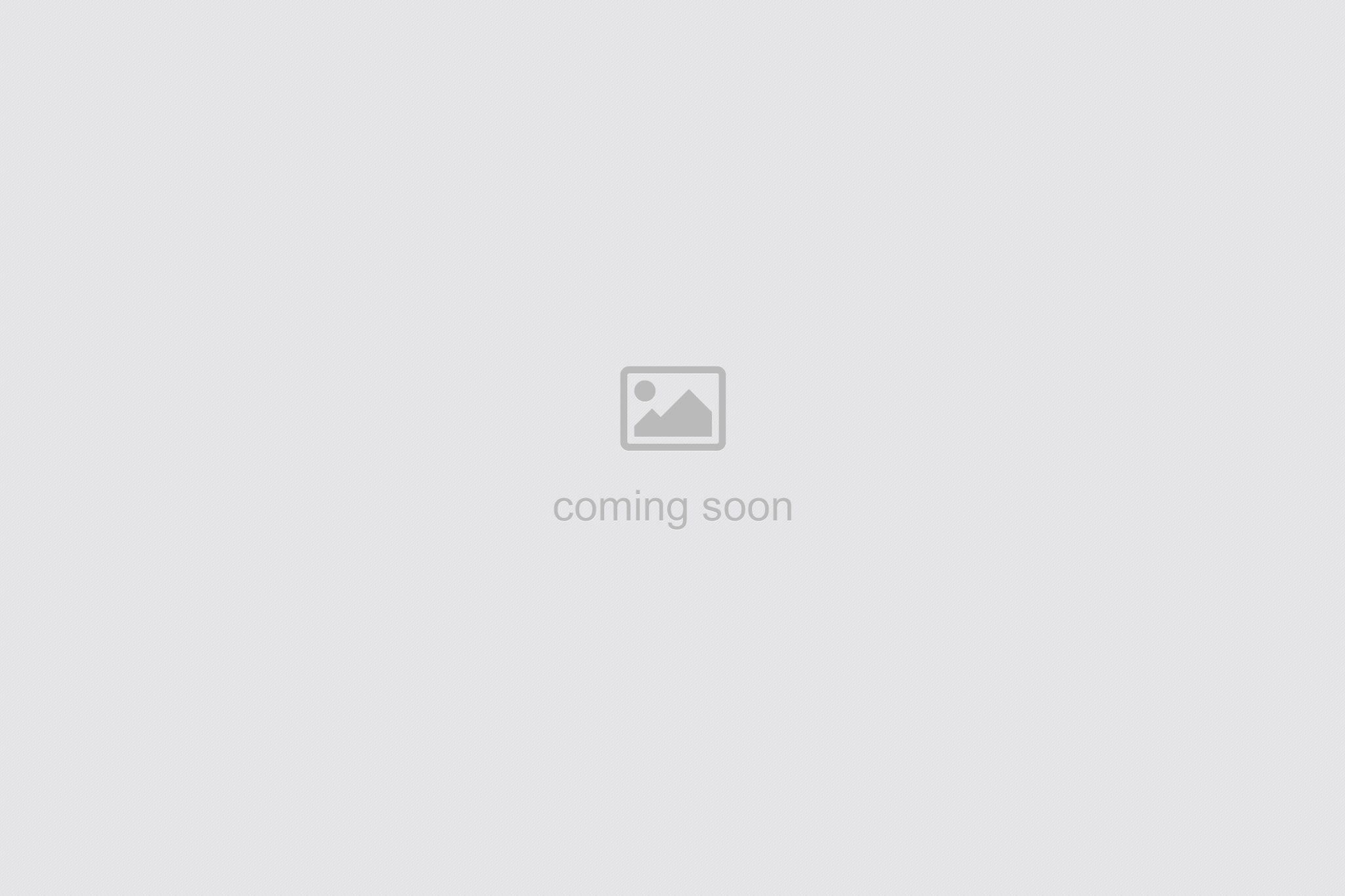It is low-cost。
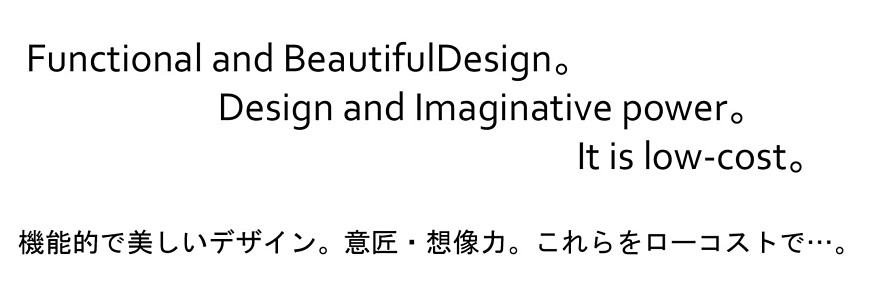
限られた予算内であれもこれも全て希望をかなえることはできません。
特に土地から探す場合、建物にかける予算は当然限られてきます。
そこでコストを抑える住まいづくりの基本的なことを述べていきます。
(A)家の形はシンプルに計画 コストダウンの大きなポイントの1つは、使う材料や工事の量を減らすことです。 シンプルな建物形状ほど、建築費を安くおさえることができます。 外壁の平面形状や屋根形状など、間取りや敷地条件を考慮してシンプルな形状に計画することです。同じ床面積の建物でも、平面形状に凹凸を設けると外壁の長さが長くなり、外壁面積が増加します。 壁の量が増えるということは、壁の材料や壁を仕上るための工事の量が増えるということです。また、基礎の外周が長くなって、その分の材料や工事の量が増えることも見逃せません。 こうした理由から、家の形が変形プランであるとコストが上がってしまうのです。 (B)仕切りの少ないオープンな間取りに計画 部屋数を多くとって仕切りを増やすと、壁や建具などの材料や工事の手間がかかるため、コストアップしてしまいます。また、部屋の数が多い分、照明器具やコンセントなども増え、設備関係の費用もかかってきます。間取りを考える際、「何部屋ほしい」というように、部屋数を多くとることを考えがちですが、実際には、部屋数が増えると、各部屋の面積は小さくなって、開放感が得られないというデメリットもあるのです。 リビング、ダイニング、キッチンをそれぞれ独立させるのではなく、広々としたLDK型にするとコストダウンとなり同時に開放感も得られます。 (C)間崩れはできるだけさけるように計画 住宅は、基本モジュールに従ってプランを作りますが、基本モジュールから外れる寸法(間崩れ)でプランを作ると、材料にロスが発生したり、既製品のサッシをカットしたり、特注対応となったりして、見えない所で余分な費用が発生します。 できるだけ基本モジュールに従ってプランを作るようにしましょう。 |